|
NAXOSレーベルから、ウィーンフィル首席ホルン奏者ヴォルフガング・トムベック氏による初のソロCDが発売されました。(2004年6月国内発売) |
| Wiener Horn <トムベックの考察>
出典: Wolfgang Tomböck, NAXOS, 8.557471 The Art of Vienna Horn 曲目解説 "Chamber Works for Horn"からの抜粋要約)
ウィンナホルン(ヴィーナーホルン)を「楽器」と呼ぶのは、かなり控えめな表現と言えるかもしれません。 ウィンナホルンは、ホルンが現代のダブルホルンに進化していく過程の楽器と位置付けられる訳ですが、これをきちんと演奏するためには、ダブルホルンに倍する十分な準備が必要です。 演奏上は、このような「音を外す」恐怖感がつきまといます。ウィンナホルンの管長は3.7mと長く、鳴らすのには、より強く正確なアムブシュアが必要となります。そういったリスクにもかかわらず、なぜ私たちはウィンナホルンを使うことにこだわりつづけるのでしょう?答えは簡単明快、「ホルンらしい音」が出るからです。柔らかく、まろやかで色彩感に満ち、それでいて合奏の中でもヴァイオリンの音をかき消してしまうことがありません。特にウィンナホルンで演奏する事を想定して作曲された、ブラームス、ブルックナー、ワーグナー等の曲にはうってつけなのです。 1つタネ明かしをしますと、ウィーンフィルでは、難しい高音域でのリスクの高いパッセージでは、ダブルホルン(*)に持ち替えることもあります。輝かしい成功というものは、取り返しのつかないミスを犯すリスクと隣あわせなのです。しかしながら、大指揮者アーノンクールなどは、ウィンナホルンでは大なり小なりのミスは避けられないものなのだというような寛容な姿勢を持っています。
ホルンの音色が最も美しく響くのはピアニシモでクラリネットのように響くときです。
オペラの中では、状況に応じていろいろと異なった働きをします。
「魔弾の射手」で森を表しているように、にロマン派の音楽においては、自然を描写するのにも、しばしば効果的に使用されます。「ラインの黄金」では変ホ長調の響きによってライン川の深々とした雰囲気が伝えられ、「カプリッチォ」では、えもいわれぬ美しさで月光の情景を醸し出しています。
「ジークフリート」でもホルンはロマンティックな描写のために使われています。勿論、ジークフリートの角笛の動機は英雄の主題です。第2幕の長い「角笛の動機」は大変な仕事で、奏者はスコア無しで、たった1人で舞台袖で構えていなければなりません。歌手は自分のパートだけ歌っていればよいのですが、こちらは舞台上で歌っている歌手の口の動きに合わせて演奏しなければならないのです。この場面はノンストップで演奏せねばならないし、ミスしようものならぶちこわしになってしまいます。
(中略)
オーケストラのレパートリーの中では、ブルックナー、チャイコフスキー、ブラームス、マーラー、R.シュトラウス等の作品の中でホルンは曲全体を支配する極めて重要な位置を占めています。
ヴォルフガング・トムベック |
| (抜粋及び翻訳:奥田安智) |
|
< 訳者あとがき > 「やられた・・・」 たかがアマチュアふぜいの者がたいそうな物言いであるが、最初の読後感がこれであった。というのも、訳者自身は、ある北欧出身のメゾ歌手の大ファンで、かねてよりそのクリスタルのように輝かしく、深く、柔く、メゾでありながら、暗く重苦しくならない声こそ、ウィンナホルン演奏上の理想だとしてイメージしていたのだが、奇しくもトムベック氏がドミンゴの声に言及している箇所は「目からウロコ」だった。 しかしイタリア系の諸役からワーグナーのヘルデン・テノールまで幅広いレパートリーをこなす、ドミンゴのつややかな声と、トムベック氏の演奏を合わせて考えれば、深く頷けるものであったし、ウィーン国立歌劇場を日常の仕事場にしているだけあって、ウィンナホルンがいかにオペラ演奏にマッチしているかを述べている部分の説得力は他の追随を許さない。
「目からウロコ」の枚挙にはいとまがないのだが、もう1つだけ、「準備段階でのミス」と「結果として違う音が出てしまったミス」を分けて記述している点をあげたい。これなどは普段単に「音を外した」で片付けてしまう人がプロ・アマ問わず多い中で、示唆に富む文章表記だと思わされた(本人にその意識はないのだろうが)。
余談だが、訳者は1997年正月にウィーン国立歌劇場で「無口な女」新演出を観る機会に恵まれた。しかも第1ホルンがストランスキー氏、第3ホルンがトムベック氏という豪華な布陣による見事な演奏であった。いかに楽器が改良されたとはいえ、本文中のドレスデン初演時の逸話を思えば、夢のような話である。
|
| 奥田安智 |
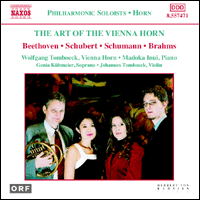 動物の角でつくられた原始的な「角笛」の時代から、ナチュラルホルンの時代を経て、今日では、ほぼ全世界においてダブルホルンが使用されています。そして世界の中で、たった1ヶ所、このグローバリゼーションにあらがっている村があります。その村こそ音楽の聖地ウィーンなのであります。
動物の角でつくられた原始的な「角笛」の時代から、ナチュラルホルンの時代を経て、今日では、ほぼ全世界においてダブルホルンが使用されています。そして世界の中で、たった1ヶ所、このグローバリゼーションにあらがっている村があります。その村こそ音楽の聖地ウィーンなのであります。